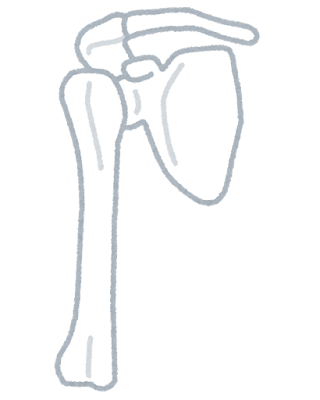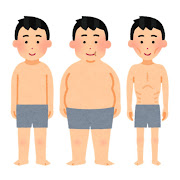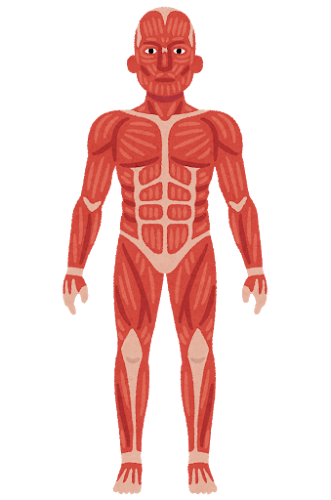何度もくりかえし読む本の一つにバーナード・ラウン博士の「医師はなぜ治せないのか」があります。現在AED(自動体外式除細動器)が病院や街のあちこちに設置され、突然の心停止からたくさんの人たちを助けられるようになってきました。そのもととなる体外除細動器を発明して、ノーベル医学賞をもらったのがラウン博士です。では、えらい学者先生の成功談の話かと思うとさにあらず、駆け出しのお医者さんが失敗を繰り返し、さまざまな問題にぶつかりながら「何が患者さんを良くしているのか」「治るきっかけとは何なのか」を探求していきます。本をのぞきながら考えたことをお話ししましょう。
1 名医の秘密
若きラウン医師の恩師レヴァイン博士は名医として有名な方でした。博士の回診では、患者さんと気軽に会話しながらちょっとしたヒントを見つけていきます。寝汗で枕が濡れている患者さんに気がつくと、枕を返して乾いたほうを上に向け「ほら、これで寝やすくなるよ!」と声をかけます。ちょっとした顔の表情や体の動きから重大な兆候を見つけ出し、まわりの医師にはなんだかわからないうちに診断を下し、さっと薬を出すとこれがまたよく効くのです。
ところがある若手の医師が「レヴァインの治療はいい加減で全然理論的じゃない」と言って、回診に参加しなくなりました。いっぽうラウン医師は(確かに診たてははっきりしないのに、なぜあんなに良く効くのだろう?)と不思議に思い、なんとかレヴァイン博士の診たての秘密を会得しようと週に六日回診に通うようになりました。
それから11年間、ラウン医師は足しげく博士のもとに通います。しだいに秘密がわかったラウン医師はなげきます。「なんと物分かりの悪かったことか!」
2 常識を乗り越える
そのころ心筋梗塞にかかった人たちはベッド上で何か月ものあいだ絶対安静を保つように指導されました。梗塞になった心筋に無理がかかれば心臓が破れて突然死をするのではないかと医師たちが恐れたためでした。
しかしラウン博士は考えます。ほんとうの急性期を過ぎたなら、むしろ体を動かして少しずつ心臓を鍛えなおし、心臓のポンプ作用を働かせたほうが患者は元気になるのでは?そこで急性期を過ぎた患者さんを慎重に動かし始めると、そのほうが早く確実に患者さんが元気になることを発見したのです。このやり方は、現在心臓リハビリテーションと呼ばれていて、心筋梗塞後の標準治療の中に組み込まれています。
3 その人を知る
病棟にひどい不整脈の患者さんが入院していました。ところが患者さんは腰痛にとても困っていて、これを何とかしてほしいと訴えていました。でも不整脈の治療で電気除細動を行う必要があったので、ラウン博士は患者さんに説明してみます。「それをやったら腰痛が治るの?」 ラウン「ええ治りますよ!」
聞いていた研修医が「そんなばかげた話は聞いたことがない!」と言いますが、博士は耳を貸さず除細動治療を行います。終わった後、患者さんは憤然としてこう言いました。「あの若い医者に言ってやるんだ!バカなのはあんたのほうじゃないか!みごとに治ったよ!って。」
見るからにはかなげな若い女性が入院していました。ちょっと歩くだけでも苦しそうにしています。心臓弁の働きが悪く心臓が弱っていると診断されていました。細かく診察したのちに、博士はこう伝えます。「いろいろ調べた結果、だいじなことがわかりました。」 「なんでしょうか?」 「あなたの手がじっと汗ばんでいることです。それ以外は何ともありません。汗のことを気にせずに、握手のときは相手の手をしっかりと握り返しましょう。あなたの問題点はそれだけです。」
入院して以来、患者さんは初めて微笑みます。そして1週間後、元気に退院していきました。
4 治癒力を発動するもの
「治せる医師・治せない医師」「医師はなぜ治せないのか」の2分冊が発刊されて20年以上たっていますが、今でも時折ページをめくっています。11年の間お師匠さんのもとに通いつめてラウン博士が会得した名医の秘密とは何だったのでしょうか?
本のなかでははっきりと述べられていませんが、オリジナル英語版の表題は「失われし治癒の技~医療における思いやり(compassion)の実践」です。このcompassionという英語は、日本語の「思いやり」よりもずっと深い意味を持つと思います。相手の心にもう一人の心が響きあい、からだに本来備わっている治癒の力が発動される。こんな感じでしょうか。ラウン博士には及びませんが、思いがけない治療の経験は医師ならだれにでもあるのでは?と考えます。仕事に疲れたとき、読むと少し元気が出る本です。